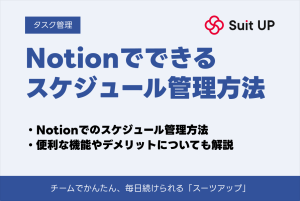業務分掌規程とは?作成方法やメリット・デメリットを詳しく解説
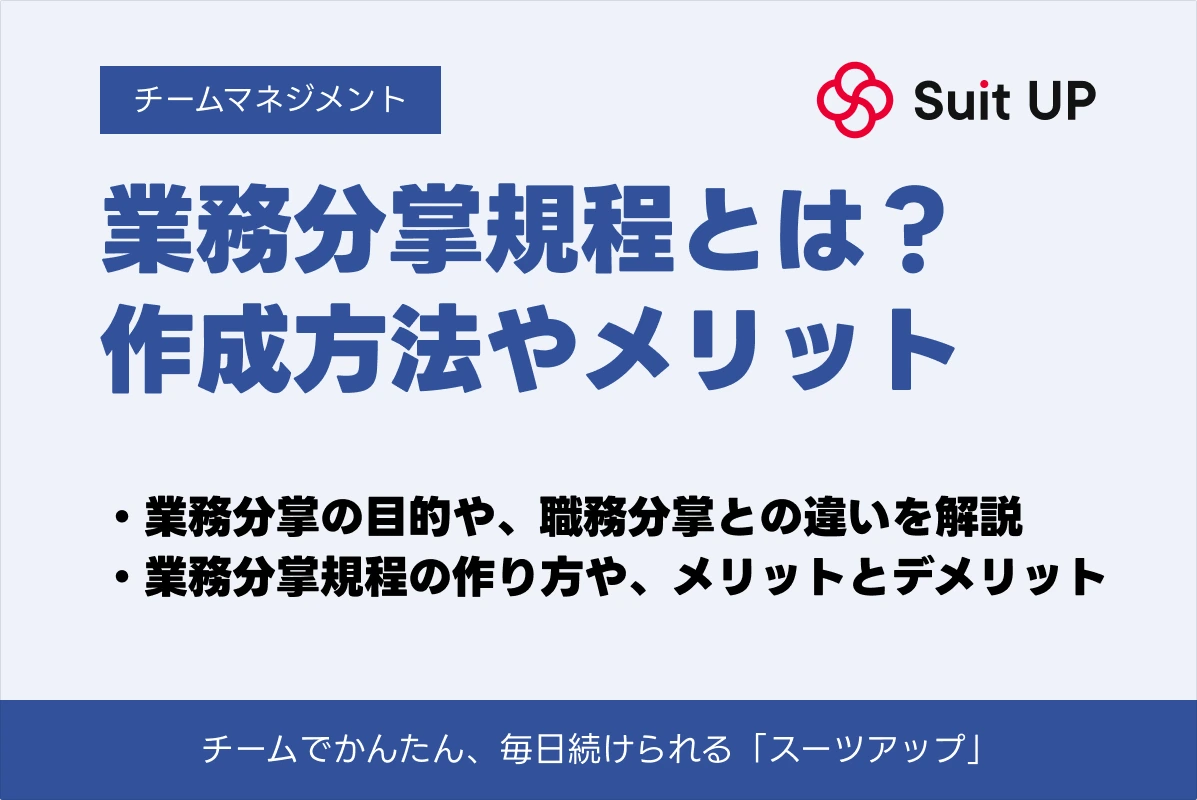
「見たことない仕事が来たけど、どの部署に相談すればいいんだろう?」
「自分の部署の担当ってどこまでなのか、線引きが曖昧だ…」
仕事の担当や役割分担に関しての悩みがあると、なかなか作業が捗らなくなってしまいますよね。
業務を明確にし、スムーズに仕事を進めていく上で役に立つのが、業務分掌規定です。
本記事では、業務分掌規定とは何か、メリット・デメリットや具体的な作り方なども含めて解説します。
職場での課題が一気に解決するかもしれないので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
業務分掌とは?
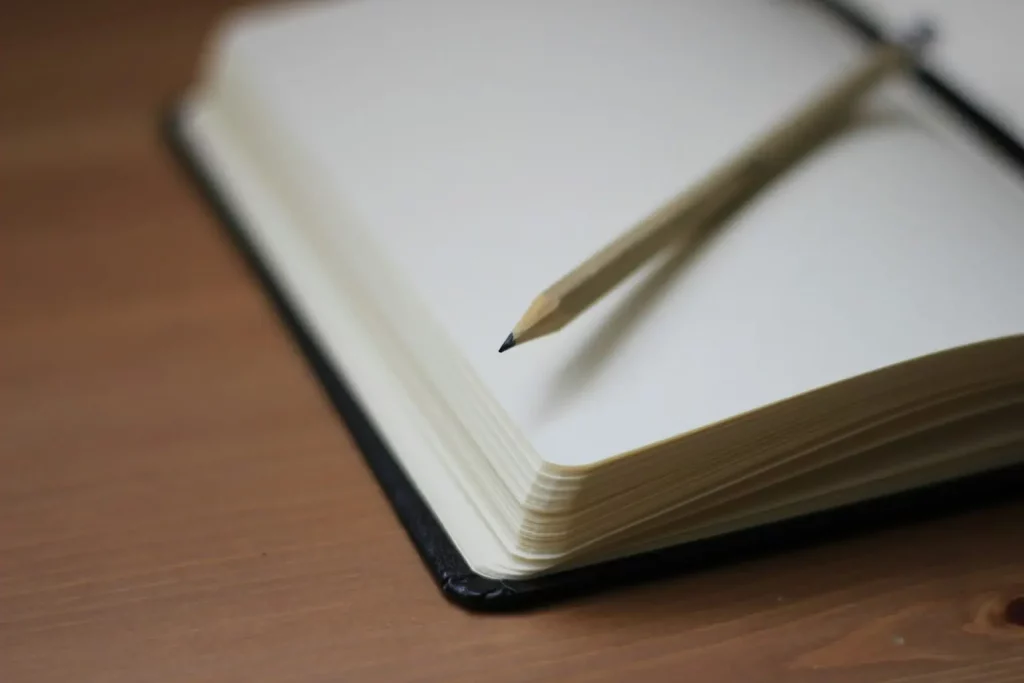
まずは、そもそも業務分掌とは何かについて確認しておきましょう。
業務分掌の目的
業務分掌の目的は、業務内容・責任・権限を明確にすることです。
会社によっては、業務の線引きが曖昧なケースもありますよね。
業務分掌を作成すると、今までどっちつかずでよくわからなかった仕事に、しっかりと担当が割り当てられます。
結果的に、仕事のスピードが桁違いに早くなるはずですよ。
業務分掌と職務分掌の違い
業務分掌とは、部署ごとの業務を明確にしたものです。
導入すると、「どこの部署に相談すればいいかわからない!」と悩むことが少なくなります。
業務フローが記載されていることも多いため、仕事が滞る心配もありません。
一方、職務分掌は、役職や担当者の役割を明確にしたもの。
導入すると、従業員が職務において期待されていることを把握しやすくなります。
担当が明確な仕事に関しては、安定したアウトプットが期待できますよ。
業務を分担するのが業務分掌、役割や責任の所在を決めるのが職務分掌と覚えておきましょう。
業務分掌規程とは?
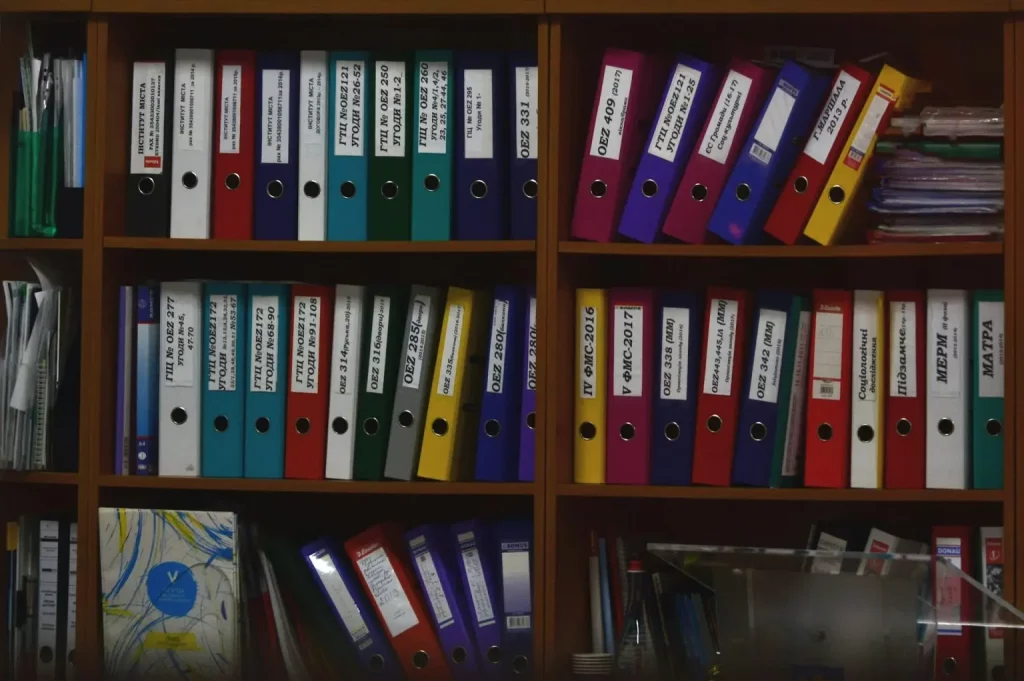
業務分掌規程とは、組織における部署・役職・担当者の業務分担を明確にし、責任や権限の範囲を文書化したものです。
困ったときにすぐに使えるように、従業員が確認しやすいところに保管し、環境を整えておくことをおすすめします。
とくに大企業では、それぞれの仕事のプロセスが長くなりがちなので、業務分掌規程の存在は必須ですよ。
柔軟な対応も求められるため、絶対視するのは禁物ですが、日常の業務を効率化する上で大きな力になります。
業務分掌規程は作るべき?中小企業でも必要?

中小企業では、臨機応変に対応することが多いため、業務分掌規定が必要ないケースもあります。
ただし、会社の成長フェイズによっても異なるので、一概に規模で要不要を判断できないことに注意しましょう。
厳格に設定しすぎると柔軟性が低下する可能性がありますが、業務の全体感が把握しやすくなるのは確かです。
リソースの少ない中小企業において、教育にかけるコストも削減できますよ。
業務分掌規定は誰が作る?
業務が複数の部門にまたがることが多いため、業務分掌規程は、代表者の間で議論しつつ作成するのが一般的です。
重要なのは、業務を理解した上で、適切に運用できる業務分掌規定を作ること。
草案作成は現業部門、職位設定は人事部門、他規定との整合性確認と修正は管理部門など、適切な役割を決めましょう。
最終的に認識合わせができるように、代表者間で議論を重ねながら整えていきます。
業務分掌規程の作り方

次に、より具体的な業務分掌規程の作成方法について紹介します。
現状の業務内容の洗い出し
まず現状の業務の洗い出しから始めましょう。
従業員が担当している業務や、仕事を進める上でよく発生する不具合などについてヒアリングします。
規模が大きくて発生頻度の高い業務からヒアリングすることがポイントです。
発生頻度が低く重要でない枝葉に力を割いても、あまり有効ではありません。
ヒアリングの際には、仕事のコアな部分について意識を向けるようにしてください。
部門ごとの責任と権限の規定
次に、部門の責任と権限を規定します。
頻度の高い業務ほど、しっかりと線引きを決めることが望ましいです。
たとえば、注文を取ってくるのは営業、金銭的な手続きを担当するのが経理など、区分けする必要があります。
責任と権限を明確にしておくと、頻繁に発生する仕事に関して無駄を省くことが可能ですよ。
運用ルールを策定する
作成した規程を遵守できるような運用ルール(フロー図)を作成しましょう。
せっかく作成しても、普通に周知するだけだと使い方がわからないため、活用されません。
実際に設定した規程をどのように運用するかまで含めて、理解してもらう必要があります。
場合によっては、担当者に向けた説明会の開催が必要かもしれませんが、一旦運用できると後が楽です。
手間暇を惜しまず、実効性を持たせられるような運用ルールを作成してください。
定期的に見直しを行う
運用が軌道に乗ったら、定期的にブラッシュアップすることも考えてください。
環境が少しずつ変化していくため、アップデートが必須です。
たとえば、スマホ・タブレットの普及により屋外でも決済できるようになりました。
紙の書類のみで運用していた時代と比べると、考えられないくらい変化しています。
見直しの周期も運用ルールとして組み込んでおくと、忘れずに済みますよ。
既定の内容を評価できる仕組みを整え、時代の流れも取り込みながら、レベルアップを図っていきましょう。
業務分掌規程のメリット

次に、業務分掌規程のメリットについて紹介します。
責任の所在が明確になる
業務分掌規程導入のメリットの1つは、どこの部門の誰が業務を担当するかが明確になること。
業務上の無駄を排除し、意思決定をスムーズにできます。
業務の譲り合いが減り、社員が力を発揮しやすくなるのもポイントですよ。
誰がやっているかが一目でわかるので、問い合わせ先を探すのもスムーズになります。
何かトラブルがあっても、事務的な手続きに時間がかからず、迅速にやるべきことに着手しやすくなるはずです。
個人の責任感が向上する
業務分掌規定があると、担当が明確になるので、仕事の責任が自分にあるという意識を持ちやすくなります。
上司任せにならず、しっかりと責任を感じながら業務に取り組めるのがメリットです。
また、上司が担当している仕事もわかりやすいため、部下も組織全体を考えた動きをすることが可能になります。
結果的に、関係各所からの信頼が集まる好循環が生まれていきますよ。
業務の属人化を防止できる
基本的に業務がオープンになっているため、属人化の防止にもなり、誰かが案件を抱え込むことがありません。
担当者だけが仕事の存在を知っているという事態が発生せず、仕事が停滞しにくくなるのも大きなメリットです。
業務が書面に明記されていると、担当者以外も部門内の仕事を確認できますよ。
たまに普段と異なる業務を経験すれば、メンバーのキャリアアップにもつながります。
退職や配置転換で人が入れ替わったときも、組織全体のパフォーマンスは変わりません。
新入社員のスムーズな育成ができる
業務分掌規程の作成で、業務の全体感がわかりやすくなることで、新入社員の育成の役立つのも、大きなメリットです。
新入社員に与えられる仕事は、簡単なものが多くなりがち…。
それぞれの仕事にしっかりとした意味づけをすることで、役割を理解しつつ仕事に取り組むことが可能になります。
早期の戦力化を図れるので、育成にかけるコストの削減が期待できますよ。
業務分掌規程のデメリット
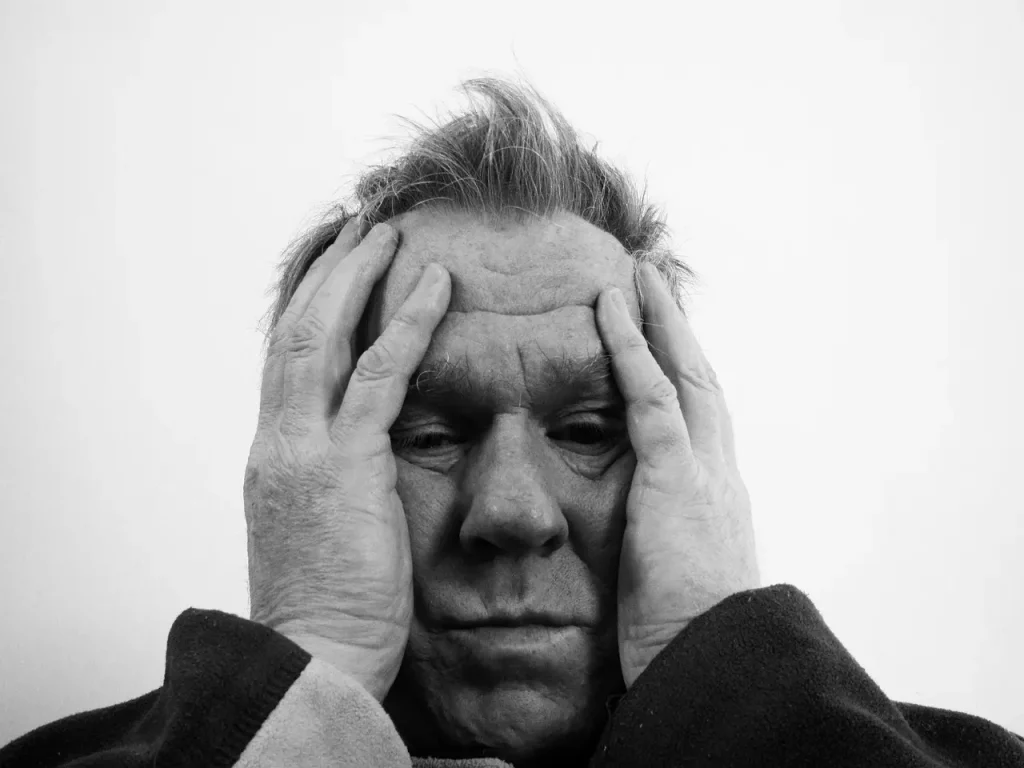
さまざまなメリットが期待できる業務分掌規程ですが、まったく問題がないわけではありません。
業務分掌規程のデメリットについても確認しておきましょう。
柔軟な対応がしづらくなる
業務分掌の活用に慣れてくると、明記されていない内容に関しては、どの部門の担当なのかがわからなくなります。
結果的に対応が遅れ、顧客に負担をかける可能性が出てくるかもしれません。
また、組織が大きくなればなるほど、運用ルールが浸透するまでに時間がかかるもの…。
担当者間で柔軟に対応できていたことが、規程の設定によって上手くいかなくなる可能性もあることに注意しましょう。
作成・運用に手間がかかる
そもそも、業務分掌規程の作成と運用に手間がかかることは否めません。
ヒアリングや業務分掌の作成・内容の周知、組織への浸透と、なかなか大変です。
企業が大きくなればなるほど、多大な労力を割くことになりかねません。
関係各所への説明と合意形成や、滞りなく周知すること、実際の運用ができているかのチェックなども必要です。
規程の運用が軌道に乗るまでは、多くのコストを割かなければならないことは、認識しておいてください。
責任転嫁が発生する
業務分掌に明記されていないイレギュラーな仕事だと、責任の押し付け合いが起こる可能性があります。
問題を解決しようという意欲がなくなり、当事者意識が薄れていってしまうことも…。
仕事の種類ごとに窓口の部門を明記しておき、漏れが発生しないようにしましょう。
また、定期的に改定することは、記載漏れを防げるだけでなく、組織の健全性確保にもつながっていきます。
こまめにブラッシュアップして、責任転嫁が発生しないような体制を整えていきましょう。
「業務分掌規程」についてよくある質問
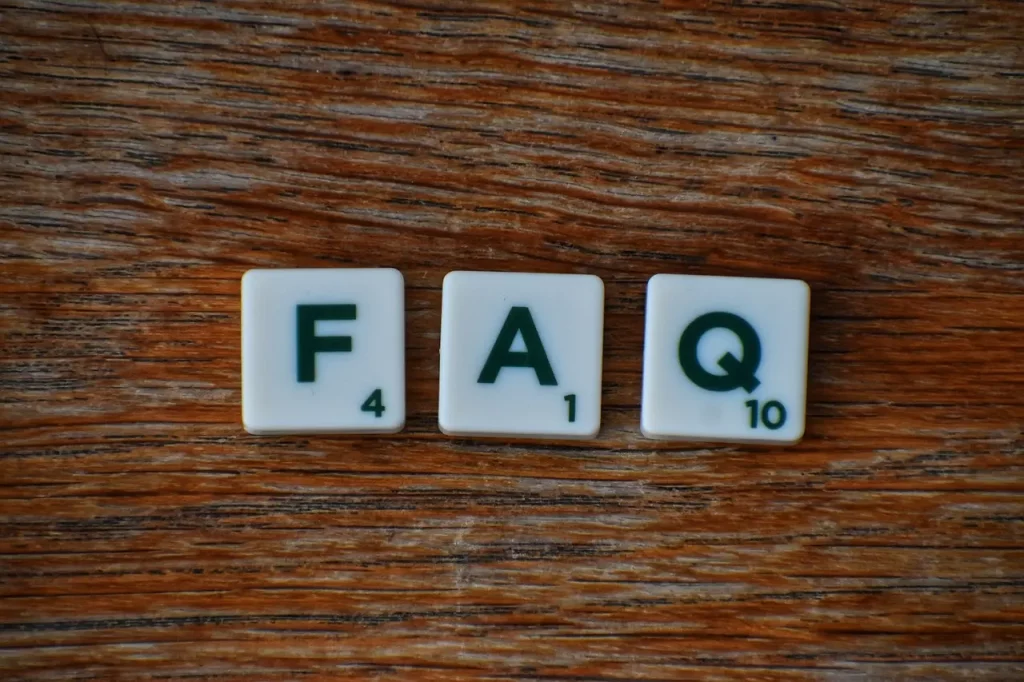
最後に、業務分掌規程について、よくある質問をまとめました。
業務分掌規定とは?
業務分掌規程とは、部署ごとに業務や権限を明確に示した文書のことです。
設定することで、成熟した企業では、円滑に組織運営ができるようになりますよ。
ただし、成長過程にある企業では、業務内容やフローが明確になっていないこともあります。
かえって運営しづらくなる可能性がある点には、注意しておきましょう。
職務分掌規定とは何ですか?
職務分掌規程は、組織内でそれぞれが果たすべき責任や職責を全うする上で必要な権限を明記したものです。
どのような仕事を誰がすべきで、どのような権限が必要かを決め、文章や表にしてまとめてあります。
必要に応じて、業務分掌規程と使い分けてください。
職務分掌は誰が作るのが良いですか?
大まかなドラフトについては、各部署の代表者や管理職以上が作成しましょう。
その上で、内容を外部の社会保険労務士にチェックしてもらう方法が一般的です。
社内の人間だけだと、専門的な知識が不足してしまいがちです。
さらに、部門ごとの利害が絡むことで客観性に欠けることもあります。
社会保険労務士にも規程の作成に関わってもらうことで、他社事例や最新法令の内容も規程に反映できますよ。
【まとめ】業務分掌規程とは?

業務分掌とは、業務内容・責任・権限を明確にすることです。
業務分掌規程を設定することで、責任の所在を明確化し、業務の属人化を防ぐことにつながります。
煩雑な仕事が増えてきたなと感じたら、導入を考えてみましょう。
作成にあたっては、大きな負荷がかかりますが、得られるメリットも大きいですよ。
コンプライアンスに厳しい昨今、従業員の責任感を育むことが必要不可欠です。
組織を健全に運営するための仕組みを導入して、会社のレベルアップを図っていきましょう。

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。
まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。