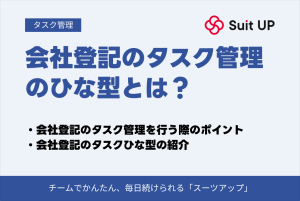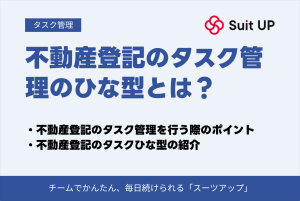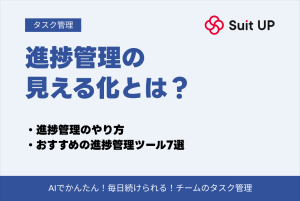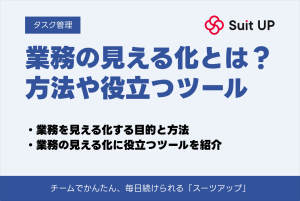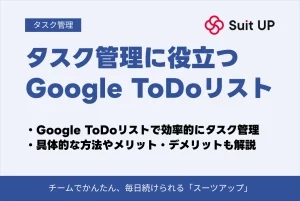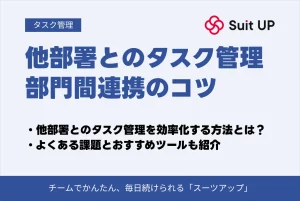古屋 星斗(一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事 )と小松裕介(株式会社スーツ 代表取締役社長CEO)によるQ&A

当社では、2025年2月26日にゲスト講師に、一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事の古屋 星斗氏を迎え、第3回目となるスーツアップ特別ウェビナー「2025年の働き方の現在地 〜構造的な人手不足と日本の進むべき道〜」を開催しました。
本稿では、中小企業の皆様にとって有益な情報が満載だった本ウェビナーの内容を、全編・後編の2回にわたりダイジェスト版としてお届けいたします。
後編は、ゲスト講師の古屋氏(一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事)と当社代表者の小松(株式会社スーツ 代表取締役社長CEO)による対談の内容です。古屋氏のご経歴は以下のとおりです。
<一般社団法人スクール・トゥ・ワーク 代表理事 古屋 星斗>

岐阜県出身。2011年一橋大学大学院社会学研究科 総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。2017年より民間研究機関に所属。労働市場分析、未来予測、若手育成、キャリア形成研究を専門とする。著書に「ゆるい職場-若者の不安の知られざる理由」(中央公論新社,2022)、「なぜ『若手を育てる』のは今、こんなに難しいのか」(日本経済新聞出版,2023)、「『働き手不足1100万人』の衝撃」(プレジデント社,2024)。
【まとめ】
-
- 人手不足は地方から都市部へ広がる「構造的な問題」である
- 生産性向上には「現場の無駄可視化」と「現場参謀」の存在が不可欠
- 多様な働き方支援と中核人材の支援の両立が企業の生き残りのカギ
- 地域課題とテクノロジー活用が、日本初イノベーションの突破口になる
省力化と賃上げ、どちらが先か?
株式会社スーツ 小松裕介(以下「小松」といいます。):今日ご視聴していただいている皆さんは民間の方々になりますが、我々がやらなければならないことはもちろん、現場の改革だと思います。一方で、マクロな目線で、例えば国はこの状況に対してどのようなアクションを取ろうとしているか、既に決まっていることや取るべきアクションについてぜひ教えていただきたいです。
一般社団法人スクール・トゥ・ワーク 古屋星斗(以下「古屋」といいます。):「生産性を上げる」ということはずっとやってきています。中小企業庁では補助金を出して生産性向上支援を行っていたり、最近ではカタログ型の補助金というのもありますね。ロボットやAIなどの製品カタログを作って、そのカタログから購入する場合は50%補助します、というもので、中小企業に対して具体的なパッケージを示して導入を勧めています。
しかし、労働政策の中心は働き手が不足する状況を前提とした政策ではなく、基本的には失業対策なんです。世界中の政府は失業対策を最低限の仕事としてやってきていると言えるでしょう。
今の日本では失業という現象が起きづらい状況になってきています。働いても賃金が全く上がらない状況などが問題となっているインフレです。補助金だけではなく、働き手がもっと得するような税制のあり方だったり、働いた方が得をする仕組み作りだったりを考えていかなければならないのではないでしょうか。頑張る企業をもっと応援するような、さまざまな税制のあり方なども必要になると思います。
地方と都市部、課題解決の優先順位は?
小松:今日は日本全体のお話をいただきましたが、東京と地方の格差もより広がっていくのかな、と感じますが、そのあたりはいかがでしょうか。
古屋:本当にそうですよね。この働き手不足の問題は、どちらかと言えば地方発の話です。これまでの社会問題との大きな違いは、東京のヘッドクォーターが分かっていないことなんです。世界最先行の労働市場の奇妙な状況が起こっているのは日本の地方なんですが、それを東京のヘッドクォーターが分からないことが、この問題の厄介な一面でもあります。
私は全国各地を回っていますが、最も共感していただくのは地方ですし、「そんなことはずっと前から思っていた」などの声をいただくのも地方の経営者からです。そういう意味では地方で一番求められていることだと思っています。

小松:私も地方で企業再生に関わっていたことがあるので共感できます。公務員やインフラで働いている人たちの仕事を効率化して、もう少し生活サービスのような仕事に携われるようにしないと回らない世の中になる、と感じています。
古屋:そうですね。生活サービスは労働集約型なので、人手がたくさん必要とされます。その状態を変えないと、特に地方では、若者全員を投入しないと高齢者の介護サービスが回らないといった状況になってしまいます。
これでは全く未来がない状態なので、やはり地域企業、特にエッセンシャルワークの生産性を本気で上げにいく必要があると思っています。
そのための仕組みとしてはまず現存のタスクをしっかり分解して、必要なタスクと不要なタスクの選別をする。必要なタスクの中で資格が必要なタスクに関しては有資格者に集中して従事していただいて、資格がなくてもできるような仕事、例えば介護の現場であれば、レクリエーションなど専門職でなくてもできること、そういう仕事は有資格者以外の、例えば地域の人たちと一緒に楽しめるような仕組みにするなどが考えられると思います。

外国人材活用の可能性と限界
小松:労働力という点で、移民に関してはどう思われますか?
古屋:外国の人と一緒に働くことは大前提としてあると思いますが、10年前と今では状況が違います。為替も影響していると思いますが、日本円で支払われる給料の魅力は大きく低下していますよね。東アジアの地政学的な状況に鑑みると、10年後の日本は賃金競争に勝てますか?疑問です。
外国人の労働力というと、韓国や台湾、シンガポール、オーストラリア、中国といった国々とインドネシアの若者を取り合う状況が考えられますが、そこでの賃金競争に日本の大手企業なら勝てるかもしれません。しかし、中小企業がこの競争にそもそも参加できるのか、と考えると、結局同じ議論になるんです。生産性を上げて賃金を上げなければならない。
小松:ここまでの話で考えると、なかなか1つの技が「ウルトラC」になることはなさそうですね。複合技で、あらゆる方向からみんなで知恵を絞る必要がありそうです。特定の業種を考えたり、都市部に集約する考えもあるかもしれません。中小企業の数を減らして大企業に寄せる、という論点もありますか?
古屋:減らすというより、互いの強さを掛け合わせて、より魅力的な会社を作っていく、ということだと思います。その会社でしかできないサービスはやはり強みになりますよね。
例えば、地下鉄のトンネル点検ができる会社ってそう多くないそうです。何社かの会社が都市部のインフラを守っている。その会社が無くなったら地下鉄は運行できなくなるわけです。
そのような会社の採用が、それぞれの会社では難しいとなると、一緒に行うとか、中核となるような中堅企業にしっかり話をして事業譲渡するとか、そういう議論をする必要が出てくると思いますね。
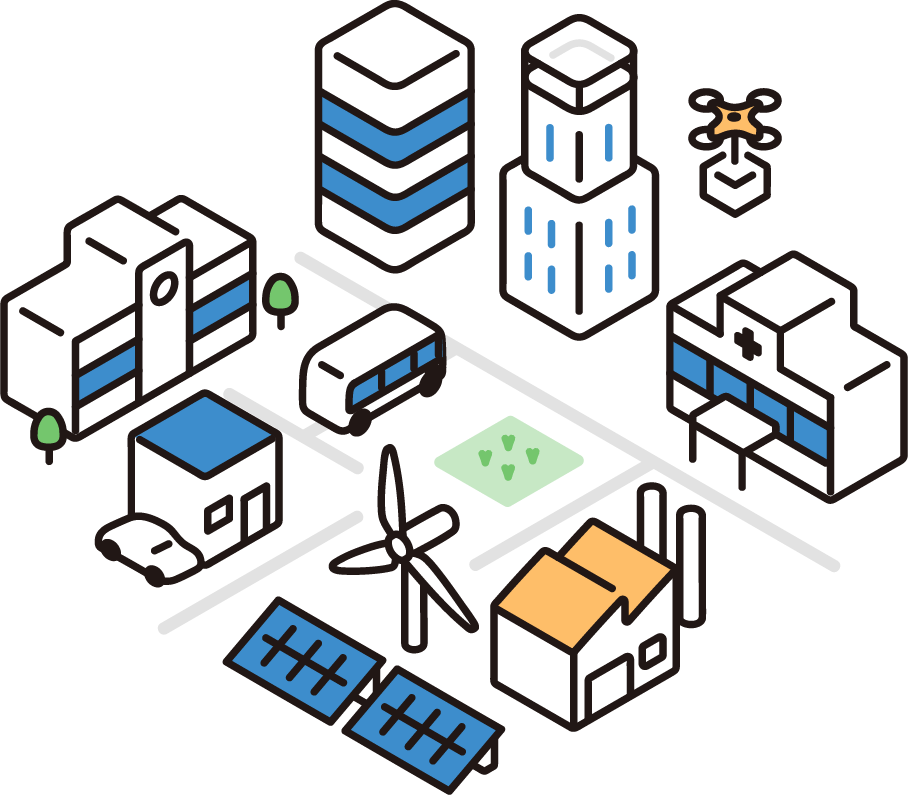
小松:先ほど、ブルームバーグや海外メディアからも注目されて記事化されている様子を拝見しましたが、話題となった本を出された後、古屋さんの話を聞きたい、講演して欲しいと依頼するのはどのような人でしょうか?大企業の人が多いですか?
古屋:この研究をし始めた頃は完全に意見が二つに分かれました。首都圏の大企業や行政の人たちは、今の人手不足は一過性のことではないか、と言っていました。一方で、現場の人や地域企業の人たちは「まさにそのとおりだから、一緒に何かやりましょう」と言ってくださっていました。
この研究を出してから、特にコロナが明けてからは、日本政府の審議会の場や大手経済団体でもお話をさせていただいていますので、共通見解がかなりできつつあると思っています。現状は誰もが直面したことがない状況であることは間違いなく、打ち手に関してはまだ共通見解までには至っていない、と感じています。
日本企業が生き残るために必要な戦略とは
小松:省力化産業という話がありましたが、省力化産業の中で日本企業が生き残るにはどうしたらいいのでしょうか。特にAIは今アメリカが強い状況ですが、その中で我々が取るべき道に関して、どのように考えていらっしゃいますか?
古屋:そうですね、AIにしろロボットにしろ、アメリカと中国が圧倒的に強いです。しかしアメリカと中国にはその省力化技術を生かすためのフィールドがないんですよ。
トラックドライバーを例に挙げると、自動運転が完全に実行できてしまったら、ドライバーは職を失うわけです。いま日本ではカルガモ輸送とか電子連結と呼ばれていて、すでに実装段階にある、3台を電子連結させて、先頭車両は有人、後の2台は無人という技術の開発が進んでいます。しかし、現場が過重労働すぎて、働き手としては助けて欲しい現実の中で、この技術に反対の声を聞くことは多くはありません。
このように労働市場が逼迫している、働き手が全然足りていないという状況が、技術革新の社会実装の速度を高める大きなパーツになると考えます。「必要は発明の母」と言いますが、作られたものを実装できる場が日本にしか存在しないといったテクノロジーが、今後おそらくたくさん出てくるのではないかと考えています。現場が本当に困っていて、働き手が限界を感じているような、AIが導入されても誰も困らない状況においては、どんどんそういう技術が生かさなければならないわけです。
日本は、そのためにどのようなことが必要かという議論が他の国よりも進みやすいと思います。社会実装に至るビジネスサービス、それは海外初となる技術になるかもしれませんが、そういうサービスが実装できるのは日本だけかもしれない、と。海外の技術だけれども使いこなせるのは日本しかないということです。
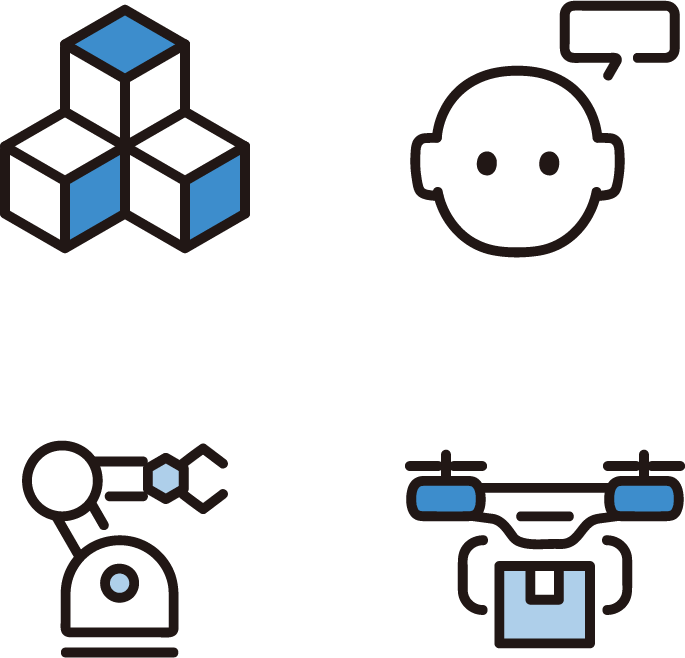
小松:当社では、来るべき省力化産業の旗手を目指して、今、タスク管理ツール「スーツアップ」を開発しています。日々「日本は課題先進国なので、省力化産業としてのタスク管理、業務の標準化という部分をAIなどテクノロジーを使いながらやれば、グローバルに行けるのではないか」と私の夢を語っています。
まさに今日の古屋さんのお話にあったとおり、最先端マーケットである日本でまず勝つ。そこでのノウハウを貯めて、グローバルで戦いたいという話に多くの方にご賛同いただいていると思っているので、今日のお話に改めて意を決した次第です。
聴講者(Aさん):技術革新によって地方の労働を支えるというお話がありましたが、最悪のケースとして、都市部への人口移動が進んだ場合、地方はどうなりますか?
古屋:働き手不足に直面しているのはエッセンシャルサービスですよね。建設、物流、医療、介護を中心としたエッセンシャルサービス。一方、地方における居住可能地域が狭まっていますよね。県庁所在地の周辺しか物流サービスが届かない状況もあったりします。
郵便局は法律でユニバーサルサービスが義務付けられているので、郵便局にコンビニを併設するなどの取り組みが行われたこともありますね。地方に対して何もアクションを起こさなかったら、買い物も郵便局、物を運ぶのも郵便局、と郵便局を中心としたエリアに人が住む、というイメージが考えられると思います。
エッセンシャルワークが届かない地域が増えるということは住める場所が減るということになります。住める場所は大都市、10万人以上の都市だけになってしまうかもしれない。その規模の都市は各都道府県に2、3つはあると思うんですけど、そこに住まないと非常に不便になってしまう社会になってしまうと考えられます。
現時点でも結構限界に近い状況にあるんです。例をあげると、秋田県ではエッセンシャルワークではなく、教員の人たちが大変な状況になっていて、小学校の先生の採用倍率が1.0倍になっています。つまり選考していられない、全員採用しないと定員が埋まらない状況なんです。地方では本当に限界を迎える現象が起こるのではないかと考えています。
小松:ありがとうございます、本当にそうですよね。地方に行くと、これから地方はどうなるのか、と今日時点でも思います。これがさらに進んだら一体どうなってしまうのだろう、限界集落が増えていくんだろうか、と感じますね。小松:ありがとうございます、本当にそうですよね。地方に行くと、これから地方はどうなるのか、と今日時点でも思います。これがさらに進んだら一体どうなってしまうのだろう、限界集落が増えていくんだろうか、と感じますね。
古屋:そうですね。スマートシュリンクといった発想をお話しされる人もいらっしゃって、私も賛成意見です。縮小することでうまく設定できる手段があるのではないかと考えています。
例えば、サービスを画一的にすれば働き手数は減るんですよね。郵便局に全部の機能を集中させてしまえば、そんなに働き手がいなくても、高齢者が多い地域でも回る地域を作れたりすると思います。
とある村の話で、スーパーマーケットもコンビニもないんですが、週2回の移動販売が来るんですね。高齢者も含め全住民がそのたびにそこに集まるので、顔見知りの井戸端話のようになって結構楽しい。さらに歯科衛生士や医師が移動販売に同行して、健康診断もしてくれたり、娯楽を企画したりもしています。
こういうスマートシュリンクみたいなあり方、若い人にとっては退屈に思えるかもしれませんが、ハッピーだと感じる人たちもいらっしゃるわけです。地方の新しいプロセス、新しい社会の作り方についての議論はあり得るのかな、と思います。
小松:聴講者の皆さんには、本日の古屋さんの話をぜひ日々の活動の生産性改善に役立てていただければと思います。古屋さん、皆さん、今日はどうもありがとうございました。
<ご案内>
本記事は、中小企業の皆様向けに開催したスーツアップ特別ウェビナーの内容をダイジェスト版としてまとめたものです。
当社では、毎月2回、中小企業の経営者やご担当者様に向けて、 日本経済の中心である中小企業等の経営改善に貢献できるようなテーマのウェビナーを主催しております。
過去のウェビナーでは、第一線でご活躍されている経営者や専門家の方々をゲスト講師にお迎えし、中小企業を取り巻く経営環境、マーケティング、デジタル・トランスフォーメーション(DX)、労働生産性の向上に繋がるマネジメントシステムの構築、M&Aなど、多岐にわたるテーマでご講演いただいております。
今後のウェビナー情報や過去のアーカイブについては、当社WEBサイトをご覧ください。
【2025年の働き方の現在地~構造的な人手不足と日本の進むべき道~】
・「2025年の働き方の現在地~構造的な人手不足と日本の進むべき道~」(ゲスト講師:一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事 古屋 星斗)
・古屋 星斗(一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事 )と 小松裕介(株式会社スーツ 代表取締役社長CEO)によるQ&A

0409-300x200.jpg)